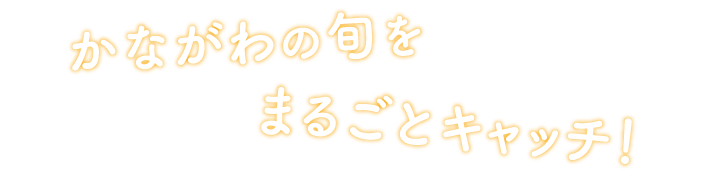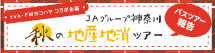2025/3/2:かながわ蔵元めぐり ~久保田酒造編~






◆県内にある13の蔵元をめぐる人気シリーズ!
相模原市緑区にある「久保田酒造」の酒造りをリサーチしました!
江戸時代末期の1844年(弘化元年)創業。
180年前から変わらぬ自然豊かな環境の中で、丹沢山系の湧き水を使い、伝統を守り
ながら銘酒「相模灘」を仕込む酒蔵です。
酒造り最盛期を迎えている蔵の中をご案内いただきました。
◆日本酒における「お米」の役割
お酒はお米の加工品。米と水と麹だけで作ります。
酒造りにおいてお米は「米麹用」、「酒母用」、「仕込み用」と大きく3つに活用されます。
それぞれを役割に合わせた米に仕上げるために重要なのが、水分のコントロール。
お米を炊くのではなく蒸す理由は、水分コントロールしやすい「外硬内軟」の米にする
ためなんです。
◆久保田酒造の酒造りを見学、体験
真冬の早朝8時。
それぞれの持ち場でスタンバイした蔵人たちが、蒸しあがりの合図で一斉に動き出し
ます。
この日蒸したのは、米麹用と仕込み用の酒米。
長野県産の美山錦600キロ。
①「ひねり餅」
まずは蒸し具合の確認。
熱々の蒸米を手のひらで潰してひねります。
お米の質感や硬さから蒸米の状態を把握すると同時に、明日の蒸米の水分量などを
決めるために行う作業なんだそう。
手触りを確認した後は、食べて食感を確認。
りゅうちゃんの感想は「お米のグミ食べてるみたい」でした。
②「放冷」
蒸したてのお米をある程度の温度に冷まし、その後の作業につなげます。
均一に冷ますためには、素早く広げ熱がこもらないよう塊をほぐす必要があります。
りゅうちゃんも蔵人と一緒に作業を進めました。
③「麹作り」、「出麹(でこうじ)」
今回は特別に「麹室(製麴室)」にも入れていただきました。
お酒の味を決める「米麹」を作る部屋で、蔵にとって最も重要といえる場所です。
室内の気温は35℃。カメラのレンズもあっという間に曇りました。
先ほど放冷した蒸米の上に、カビの一種である「黄麹菌」を振ります。
菌は粉状で軽いため、振っている間や蒸米の上に落ちて定着するまで蔵人も静かに
動きを止めます。
菌を振る蔵人の所作。
ゆっくりと舞い、降り注ぐ菌の様子は厳かで神秘的な光景でした。
「まるで神事をしているよう」りゅうちゃんの言葉が全てを表現していました。
久保田酒造の特徴は「突きハゼ麹」を使った酒造り。
蒸米全体に菌が回っていない状態の麹のことで、米麹に付いている麹菌の量が少ない
ほど、綺麗で香り高い日本酒ができると言われています。
その味は...栗のような甘さ!
完成した麹をほぐし冷ます「出麹(でこうじ)」作業も体験させていただきました。
④「仕込み」
本日は3段仕込みの1段目「添え掛け」の日。
蔵人たちは先ほど放冷した蒸米を担ぎ、酒母の入った1トンタンクに次々と投入
していきます。
タンクを混ぜ(櫂入れ)ているのは、蔵元であり杜氏の久保田徹さん。
思い通りの発酵を進めるために重要なのは「温度」と話します。
一日2回(朝夕)全タンクで櫂入れを行い、温度管理や醪(もろみ)の分析等を
しています。
杜氏は蔵における酒造りの監督。
全責任を負います。
徹さんは酒造りが行われる秋口~春先まで、1日も休まず酒造りをしていると
お話してくれました。
⑤「洗濯」
作業する蔵人の中に「相模灘」の法被を着た人物が...
お手伝いに来たちゃーはんでした。
酒造りでは蒸米などで使った布などを「押し洗い」します。
米を蒸すときに使った熱湯をポンプで汲み上げ再利用。
熱湯を使うことで消毒もでき、かつ汚れ落ち効果もアップします。
そして水ですすいで絞ったら作業は完了。
酒の味に影響させないよう湯と水だけで洗います。
二人もしっかりお手伝いしました。
⑥ 翌日の蒸米の準備「洗米」「脱水」「浸漬」
理想的な蒸米に仕上げるためには、当日の気温を考慮した上で最適な水分量を
導き出す必要があります。
繊細で緻密な計画・作業の連続に圧倒された二人でした。
◆「相模灘」の味
米違いの純米酒を飲み比べました。
お米の違いで香りも味も大きく変わります。
久保田酒造の酒粕を使ったポテトサラダの味も絶品でした。
それぞれに合う「酒の肴」を見つけるのも「かながわの酒」の楽しみ方の一つ
かもしれません。
築180年の母屋は現在直売所になっています。
歴史を感じる古民家で販売するさまざまな「相模灘」。
皆さんにぜひ味わっていただきたい銘酒です。
今回ご紹介しきれなかった商品も多数販売しています。
◆女将の想い、蔵元の想い
日本酒が大好きと話す女将の加奈さん。
どのお酒のことを尋ねても、笑顔でその特徴と美味しさ教えてくれます。
妻として夫・徹さんの体を心配しつつ、酒造りを全力でサポートします。
母として2人の子供を育て、酒蔵からの恩恵を子供たちに伝えています。
「息子が2歳の頃から酒造りするって言ってくれてるんです」と笑顔を見せながらも
「好きな道に進んでくれればいいんですけどね」と気持ちを教えてくれました。
杜氏である徹さんは加奈さん、蔵人らへの感謝を口にしつつ
「伝統を守りながら、このままの酒造りを続けていきたい」と話します。
7代目蔵元がひたむきに醸す「相模灘」―――
蔵の歴史と伝統、そして酒造りの奥深さ。
また一つ、神奈川の酒蔵の魅力を感じたひとときでした。






◇久保田酒造
住所:相模原市緑区根小屋702
TEL:042-784-0045
HP:https://www.tsukui.ne.jp/kubota/
Instagram:https://www.instagram.com/sagaminada_kubotashuzo?igsh=MWNpeWV0MGEyM3preg%3D%3D&utm_source=qr
◇神奈川県酒造組合
県内13の酒蔵のお酒が購入できます!
住所:厚木市旭町1-17-11
TEL:046-228-6194
HP:https://www.kanagawa-jizake.or.jp
企画:JAグループ神奈川
- 放送内容2026/2/22:
神奈川から世界へ「湘南はるみライスウイスキー」 - プレゼント2026年2月のプレゼント
- 動画2026/2/15:人も自然もいきいきと ∼丹沢大山・厚木∼
- 放送内容2026/2/15:人も自然もいきいきと ∼丹沢大山・厚木∼
- プレゼント2026年2月のプレゼント
- レシピ2026/2/15:郷土料理 かてめし
- レシピ2026/2/15:切り干し大根のサラダ
- レシピ2026/2/15:豆腐のパンナコッタ ∼いちごソース添え∼
- 動画2026/2/8:キュンとすっぱい!湘南潮彩レモン
- 放送内容2026/2/8:キュンとすっぱい!湘南潮彩レモン
- プレゼント2026年2月のプレゼント
- レシピ2026/2/8:レモン鍋
- 動画2026/2/1:かながわ蔵元めぐり「黄金井酒造 立春編」